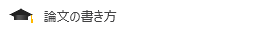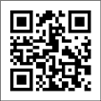資料紹介
トランスジェンダーと医療
1.はじめに 『ロバート・イーズ』(原題:Southern Comfort)というドキュメンタリー映画がある。二児をもうけた後、三十代半ばで女性から男性に性別を移行し、アメリカ南部で農場を経営する、カウボーイ・ハットが似合う武骨な男。しかし、彼に残された最後の「女」である卵巣がガンに冒され、同じトランスジェンダーの友人たちに見守られながら、自宅で一生を終える。 最期に至るまで自宅にとどまり続けたのは、あるいは望んでのことだったかもしれない。しかし、彼が言うには、病院に入院しようにも、病院が他の患者の苦情や世間の風評を恐れて、次々と入院を拒む。費用は確実に払うと言っても、相手にすらされない。そうこうしているうちに、ガンは末期に至る。女性から男性(FTM)のトランスジェンダーが行う乳房切除手術についても、トランスジェンダーが受けるなら、同じ手術を普通の女性が受ける時の数倍の費用を請求され、かつ手抜きも目立つ事実が、友人により明らかにされる。 性的マイノリティの権利擁護が進んでいるといわれるアメリカにおいても、まだトランスジェンダーが二級市民としてしか扱われず、必要な医療サービスを十分に受けることができないという、厳しい現実がある。
ロバートのようなトランスセクシュアルに限らず、この世の中には、広く生まれながらの性別から離れ、反対の性別を社会的に選択する者、伝統的でない性別表現や性別役割を生きる者が存在する。これらの者を、さしあたりトランスジェンダー(性別越境者)と呼ぶことにする。 これまで、トランスジェンダーの医療といえば、主に性別の再指定、すなわちホルモン療法や性別適合手術(俗にいう性転換手術)により、身体の外観を自ら望む性別のそれに適合させるための医療のことを指していた。むろん、この点についても日本において近年、急速に「性同一性障害」治療体制が確立されたとはいえ、まだクライエントが十分に満足を得られる医療が提供されているとは言い難い。この点についてものちほど少しばかり触れることになると思うが、本章で私が論じるのはその意味での医療ではない。問題にしたいのは、風邪や胃炎、ガンといった、トランスジェンダーに固有とはいえない、一般的な疾患にかかったときに受ける医療であり、加齢や身体的な障害によりサポートが必要になった時の介護のことである。
しかしながら、この点については、トランスジェンダー自身の意識もまだ高いとはいえない。もちろん、自らの身体の外観を望みの性別のそれに適合させるという課題が多くを占め、自らが一般的な疾患にかかるということにまで思い至らないということがあるかもしれない。 ただ、これまでよく言われていたのは、健康保険証に記載された性別が変われば、望みの性別において医療が受けられるのだから、健康保険証の性別表記のもとになっている戸籍上の性別(厳密には続柄表記の一部)の訂正または変更を求めることが先決であり、また解決策はそれに尽きる、という議論である。実際、映画『ロバート・イーズ』が日本で公開された時も、まず戸籍の変更を認めるべきという流れになり、医療機関一般における性的マイノリティの受け入れについての議論は、決して深まったとはいえなかった。
この点、二〇〇三年に成立、翌年施行された「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」)により、限定的ながらも法律上の性別変更が認められるようになった。戸籍の性別が変わればすべて解決するという議論によれば、少なくとも性別変更が認められた者については
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
トランスジェンダーと医療
1.はじめに 『ロバート・イーズ』(原題:Southern Comfort)というドキュメンタリー映画がある。二児をもうけた後、三十代半ばで女性から男性に性別を移行し、アメリカ南部で農場を経営する、カウボーイ・ハットが似合う武骨な男。しかし、彼に残された最後の「女」である卵巣がガンに冒され、同じトランスジェンダーの友人たちに見守られながら、自宅で一生を終える。 最期に至るまで自宅にとどまり続けたのは、あるいは望んでのことだったかもしれない。しかし、彼が言うには、病院に入院しようにも、病院が他の患者の苦情や世間の風評を恐れて、次々と入院を拒む。費用は確実に払うと言っても、相手にすらされない。そうこうしているうちに、ガンは末期に至る。女性から男性(FTM)のトランスジェンダーが行う乳房切除手術についても、トランスジェンダーが受けるなら、同じ手術を普通の女性が受ける時の数倍の費用を請求され、かつ手抜きも目立つ事実が、友人により明らかにされる。 性的マイノリティの権利擁護が進んでいるといわれるアメリカにおいても、まだトランスジェンダーが二級市民としてしか扱われず、必要な医療サービスを十分に受けることができないという、厳しい現実がある。
ロバートのようなトランスセクシュアルに限らず、この世の中には、広く生まれながらの性別から離れ、反対の性別を社会的に選択する者、伝統的でない性別表現や性別役割を生きる者が存在する。これらの者を、さしあたりトランスジェンダー(性別越境者)と呼ぶことにする。 これまで、トランスジェンダーの医療といえば、主に性別の再指定、すなわちホルモン療法や性別適合手術(俗にいう性転換手術)により、身体の外観を自ら望む性別のそれに適合させるための医療のことを指していた。むろん、この点についても日本において近年、急速に「性同一性障害」治療体制が確立されたとはいえ、まだクライエントが十分に満足を得られる医療が提供されているとは言い難い。この点についてものちほど少しばかり触れることになると思うが、本章で私が論じるのはその意味での医療ではない。問題にしたいのは、風邪や胃炎、ガンといった、トランスジェンダーに固有とはいえない、一般的な疾患にかかったときに受ける医療であり、加齢や身体的な障害によりサポートが必要になった時の介護のことである。
しかしながら、この点については、トランスジェンダー自身の意識もまだ高いとはいえない。もちろん、自らの身体の外観を望みの性別のそれに適合させるという課題が多くを占め、自らが一般的な疾患にかかるということにまで思い至らないということがあるかもしれない。 ただ、これまでよく言われていたのは、健康保険証に記載された性別が変われば、望みの性別において医療が受けられるのだから、健康保険証の性別表記のもとになっている戸籍上の性別(厳密には続柄表記の一部)の訂正または変更を求めることが先決であり、また解決策はそれに尽きる、という議論である。実際、映画『ロバート・イーズ』が日本で公開された時も、まず戸籍の変更を認めるべきという流れになり、医療機関一般における性的マイノリティの受け入れについての議論は、決して深まったとはいえなかった。
この点、二〇〇三年に成立、翌年施行された「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」)により、限定的ながらも法律上の性別変更が認められるようになった。戸籍の性別が変わればすべて解決するという議論によれば、少なくとも性別変更が認められた者については、問題はすべて解決済みということになる。 しかし、後に述べるような、特例法の厳格な要件をすべて満たす者は、トランスジェンダーの中でも数が限られている。身体をとってみても、たとえ「性同一性障害」治療を受けている者に限ったとしても、性別適合手術まで受け、生殖器や身体の外観を完全に変える者ばかりというわけではない。アイデンティティとなると、典型的な男性または女性の自己規定をもつ者だけでなく、両方の自己規定をもつ者、いずれでもないと規定する者など、さまざまである(従って本文で、あくまで性別「越境」者=トランスジェンダーという括りは暫定的なものでしかない)。 また、たとえ特例法により法律上の性別を変更した者であっても、生まれながらの女性や男性とは異なった医学的配慮が必要である場合もある。現在の特例法の要件では、生殖能力の喪失が要件とされているが、これは必ずしも内性器の摘出まで要求するものでなく、ホルモン療法で生殖能力は失うが、それを体内に残存させている者が存在しうる。また、変更前の性別における生活習慣と、疾患との関連性が問題になることもある。例えば、喫煙、飲酒の影響は、やはり変更前の性別が男性であった場合には、多く考慮する必要があろう。
これらの者は既存の医療システムの中で、いかなる医療サービスを受けうるのであろうか。近年医療の専門家側からも患者側からも言われる、「性差医療」においては、いかなる位置を占めるのであるのだろうか。 医療が患者に対し可能な限り最良のケアを行うべき存在である限り、患者の属性に従ってきめ細かなサービスを提供するのは、一つの方法としてあり得るかもしれない。しかし、そこからさらに排除される者が生み出されるなら、それこそ人の命に差をつけることになり、本末転倒である。 むしろ、必要とされるのは、患者の多様性の存在を前提として、さまざまなアイデンティティ、身体的属性をもつ者が、平等にアクセスする機会をもち、必要なサービスを受けることができる医療を求めることではなかろうか。 本稿では、トランスジェンダーとさしあたり言われる人々が、医療サービスを受ける際に直面する諸問題について考察する。 2.現在のトランスジェンダーの置かれている位置 ここ十数年において、トランスジェンダーを取り巻く状況には大きな変化があったといえる。「性同一性障害」という形ではあるが、社会の側の受け入れが進んだことは事実である。しかし、それですべてが解決したわけでもなく、また「性同一性障害」という形で受容されたがゆえの、新たな問題点も生じている。この節では、トランスジェンダーと医療について論じる前提として、ここ十数年のトランスジェンダーを取り巻く状況の変化を、簡単に振り返ってみることにする。 日本におけるトランスジェンダーの歴史は、古くて新しいところがある。すなわち、その存在は欧米にくらべて、古くから独自のコミュニティを形成し、一般社会にも存在それ自体は認識されていた。にもかかわらず、権利擁護が叫ばれたのはここ十年少しのことである。 日本において、風俗産業の世界では、戦後すぐより、独自のトランスジェンダーのコミュニティが形成されていたと言われる。古くはゲイボーイ、ある時期からはニューハーフと呼ばれる男性から女性(MTF)のトランスジェンダーや、オナベと呼ばれるFTM、あるいは女装者によるコミュニティが、少なくとも一九五〇年代には、東京や大阪といった大都市に存在したと言われる。そして、コミュニティに共有されている情報を頼りに、国内外の医院で、ホルモン剤を入手したり、性転換手術に臨んだりする者が現れるようになる。
しかし、一九六九年に言い渡された「ブルーボーイ事件」判決で、性転換手術を行った医師に、優生保護法(現:母体保護法)違反で有罪が言い渡される。判決の内容を仔細に読むと、必ずしも性別の再指定が全面的に否定されているわけではない。ただ、現段階では、治療の基準等が整備されておらず、時期尚早である、というものであった。しかし結果的に、同判決はトランスジェンダーの性別の再指定のための医療と権利擁護を、長期にわたり闇に葬ることになる。以後の医学界において、性別の再指定がタブー視されることになったのである。ごくわずかに、公には知られていない、「闇」と呼ばれる形で、ホルモン療法や性転換手術が行われる時期が、以後およそ三十年近くにわたり続くことになるのである。 一九九〇年代に入り、ジェンダーフリー、男女共同参画の進展や、ゲイ・リブ、多文化主義の流れの中で、トランスジェンダーについても社会的な顕在化の動きが起こる。蔦森樹『男でも女でもなく』(勁草書房)、虎井まさ衛『女から男になったワタシ』(青弓社)などの、立場を異にする当事者の自伝が相次いで出版され、またパソコン通信・インターネット上の情報サイトや、リアルでの自助グループも次々に誕生した。
しかし、この時期においてやはり大きな影響があったのは、「性同一性障害に関する答申と提言」であろう。一九九六年の埼玉医科大学倫理委員会の答申を受けて、日本精神神経学会が公表したこの「答申と提言」を受けて、翌年「性同一性障害の診断と治療に関するガイドライン」が制定され、性別適合手術(性転換手術)の合法化を含む、トランスジェンダーの性別の再指定に一定の道筋がつけられた。また、これを機に「性同一性障害」について、マスコミ各社が大きく報道したことにより、一般大衆にもかれらが抱える問題が広く認識されるきっかけがつくられたと言える。 さらに、二〇〇二年、東京都小金井市を皮切りに地方公共団体で、「性同一性障害者」に配慮する形で、公的書類の性別欄削除の動きが高まる。また同時に、地方議会レベルで、「性同一性障害を抱える人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書」が提出されるに至る。そして、二〇〇三年七月、「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」が国会で成立、翌年から施行され、法律上も性別の変更が認...