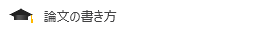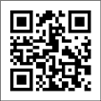資料紹介
進化論への道程
チャールズ・ダーウィン Charles Darwin(1809-1882)
『ビーグル号航海記』
Journal of Researches into the Geology and Natural History of the countries visited during the Voyages of the H.M.S. Beagle Round the World(1839)
◆作品紹介
1831年、イギリス海軍は木造帆船の軍艦ビーグル号による南アメリカおよび太平洋地域の調査探検を企てた。艦長はフィッツ・ロイであった。この調査船に博物学者として乗り組んだのが、当時弱冠22歳、ケンブリッジ大学で神学を学んだアマチュア博物学者のチャールズ・ダーウィンであった。ビーグル号は1831年12月にイギリスを出発し、1836年10月に帰国するまでの約5年間、南アメリカ、南太平洋、オーストラリア、インド洋などを調査したが、その間ダーウィンは各地の地質、生物を詳しく観察し記録した。
ダーウィンはビーグル号に積み込んだ書物、例えば、博物学者A.フンボルトの『南アメリカ旅行記』や地質学者C.ライエルの『地質学原理』を手がかりにしながら、熱心に各地を探検調査した。また、ダーウィンは航海の途中、しばしば大陸の内陸部に足を踏み入れて長期にわたる調査旅行を企て多くの標本を収集した。このような調査を通じて、ダーウィンは多くの絶滅した動物の化石を発見するとともに、動物や植物の地理的分布に注目し、生物とその生息環境との相互作用に深い関連があることに気付くに至った。
ダーウィンは、各地で生活する人々についても民俗学的かつ人類学的な関心から観察し記録しているが、特に南アメリカ最南端に位置するフェゴ島の原住民に関する記述は興味深い。というのも、艦長フィッツロイは前回の調査の際、フェゴ島の原住民4人をイギリスに連れ帰っており、今回の航海の目的の一つは、イギリスで英語を覚えるなど「文明化」した彼らを、イギリス人宣教師とともに故郷に連れ戻すことであったからだ。
このような多くの経験を積み、航海を通じて博物学者として成長したダーウィンは、1835年9月、南アメリカ大陸から約1000キロメートル離れ、赤道直下に位置するガラパゴス諸島にたどりついた。ここで彼はきわめて奇妙な動植物に出会った。サボテンを食べる巨大なゾウガメがおり、しかも、島々によってゾウガメの甲羅の形状は異なっている。サボテンを食べるリクイグアナがいる一方、海辺で海草を食べるウミイグアナがいる。また、住む場所と食する餌によって微妙にくちばしの形状が異なる小鳥(フィンチ)が観察された。地質学的には非常に新しいガラパゴス諸島におけるこれらの固有種の存在は、ダーウィンに「種の誕生」という「神秘中の神秘」に対する貴重なヒントを与えてくれたのである。
◆読み方
本書は、ビーグル号による航海の記録を日記の体裁をとってまとめたものである。当初、フィッツ・ロイの著作の一部として世に出たが、1845年に独立の著作として改訂版が出版された。通常、流布しており、また邦訳の底本となっているのは、この改訂版である。ダーウィンは、本書の執筆・出版を通じて、自然選択による種の進化というアイデアを育むとともに、博物学の世界に確固たる地歩を築いた。
航海記は全23章から成る(改訂版では全21章、以下同様)。第1章から18章(16章)までは南アメリカ大陸の各地の様子が詳細に報告され、第20章(18章)から第23章(21章)
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
進化論への道程
チャールズ・ダーウィン Charles Darwin(1809-1882)
『ビーグル号航海記』
Journal of Researches into the Geology and Natural History of the countries visited during the Voyages of the H.M.S. Beagle Round the World(1839)
◆作品紹介
1831年、イギリス海軍は木造帆船の軍艦ビーグル号による南アメリカおよび太平洋地域の調査探検を企てた。艦長はフィッツ・ロイであった。この調査船に博物学者として乗り組んだのが、当時弱冠22歳、ケンブリッジ大学で神学を学んだアマチュア博物学者のチャールズ・ダーウィンであった。ビーグル号は1831年12月にイギリスを出発し、1836年10月に帰国するまでの約5年間、南アメリカ、南太平洋、オーストラリア、インド洋などを調査したが、その間ダーウィンは各地の地質、生物を詳しく観察し記録した。
ダーウィンはビーグル号に積み込んだ書物、例えば、博物学者A.フンボルトの『南アメリカ旅行記』や地質学者C.ライエルの『地質学原理』を手がかりにしながら、熱心に各地を探検調査した。また、ダーウィンは航海の途中、しばしば大陸の内陸部に足を踏み入れて長期にわたる調査旅行を企て多くの標本を収集した。このような調査を通じて、ダーウィンは多くの絶滅した動物の化石を発見するとともに、動物や植物の地理的分布に注目し、生物とその生息環境との相互作用に深い関連があることに気付くに至った。
ダーウィンは、各地で生活する人々についても民俗学的かつ人類学的な関心から観察し記録しているが、特に南アメリカ最南端に位置するフェゴ島の原住民に関する記述は興味深い。というのも、艦長フィッツロイは前回の調査の際、フェゴ島の原住民4人をイギリスに連れ帰っており、今回の航海の目的の一つは、イギリスで英語を覚えるなど「文明化」した彼らを、イギリス人宣教師とともに故郷に連れ戻すことであったからだ。
このような多くの経験を積み、航海を通じて博物学者として成長したダーウィンは、1835年9月、南アメリカ大陸から約1000キロメートル離れ、赤道直下に位置するガラパゴス諸島にたどりついた。ここで彼はきわめて奇妙な動植物に出会った。サボテンを食べる巨大なゾウガメがおり、しかも、島々によってゾウガメの甲羅の形状は異なっている。サボテンを食べるリクイグアナがいる一方、海辺で海草を食べるウミイグアナがいる。また、住む場所と食する餌によって微妙にくちばしの形状が異なる小鳥(フィンチ)が観察された。地質学的には非常に新しいガラパゴス諸島におけるこれらの固有種の存在は、ダーウィンに「種の誕生」という「神秘中の神秘」に対する貴重なヒントを与えてくれたのである。
◆読み方
本書は、ビーグル号による航海の記録を日記の体裁をとってまとめたものである。当初、フィッツ・ロイの著作の一部として世に出たが、1845年に独立の著作として改訂版が出版された。通常、流布しており、また邦訳の底本となっているのは、この改訂版である。ダーウィンは、本書の執筆・出版を通じて、自然選択による種の進化というアイデアを育むとともに、博物学の世界に確固たる地歩を築いた。
航海記は全23章から成る(改訂版では全21章、以下同様)。第1章から18章(16章)までは南アメリカ大陸の各地の様子が詳細に報告され、第20章(18章)から第23章(21章)までは太平洋およびインド洋各地の様子が報告される。それぞれに興味深いが、何と言っても圧巻は第19章(17章)のガラパゴス諸島の観察記録であろう。ビーグル号の航海は、「種の起源」探索の発端となったのである。
◆作者の履歴
ダーウィンは、裕福な医者の家庭に生まれた。祖父エラズマス・ダーウィンは生物進化論にも通ずる著作もある有名人であった。ダーウィンはエディンバラ大学で医学を志したが、途中、ケンブリッジ大学に転じて神学を修めた。ダーウィンは、片田舎の牧師をしながら自然観察に勤しむという人生設計を描いていたと思われるが、ビーグル号による世界一周の探検調査の機会が与えられたことによって、彼の人生は大きく変化した。
帰国後、ロンドンに居を構えたダーウィンはビーグル号の調査に関する報告書をまとめるとともに本書『ビーグル号航海記』を執筆出版した。結婚後、ロンドンを離れてダウンに引きこもったダーウィンは、終生この地で過ごし、大学教授などといった定職に就くこともなく、博物学研究に専念した。
◎読書案内
Journal of Researches, Part one and two(The Works of Charles Darwin, vol.2-3), (William Pickering, 1986)
島地威雄訳『ビーグル号航海記(上・中・下)』(岩波文庫,1959-1961)
八杉龍一訳『種の起原(上・下)』(岩波文庫、1990)
◎テキストの引用
The natural history of this archpelago is very remakable: it seems to be a little world within itself; the greater number of its inhabitants, both vegetable and animal, being found nowhere else.
この島々の自然誌は、いちじるしく珍奇なものである。この群島はそれ自身で一つの小さな世界をなしている。この群島の生物は、植物であれ動物であれ、他では見ることができない。
神秘中の神秘の解明
チャールズ・ダーウィン Charles Darwin(1809-1882)
『種の起原』
On the Origins of Species by means of Natural Selection(1859)
◆作品紹介
イギリスの軍艦ビーグル号による5年にわたる調査旅行によって「神秘中の神秘」とも言うべき「種の起原」という問題を解明するためのヒントを得たダーウィンは、帰国後、この問題について熟考を重ねた。そして1838年、T.マルサスの『人口の原理』を読んだダーウィンは、人間の社会に見られる生存闘争、すなわち限られた食糧をめぐる多数の人間による熾烈な競争が、生物の世界で普遍的に見ることができるということに気付いた。生物の世界は、一般に多産であるが、多く生まれた個体のうち成長して子孫を残すものは限られている。成長して子孫を残す個体と、子孫を残すことのできない個体の差はどこにあるか。換言すれば、生存闘争において何が勝者と敗者を分けるのだろうか。
同じ親から生まれた個体にも微妙な差異、変異がある。食糧獲得などの面で、生物が生息している自然環境に適合した変異をもった個体は生き延びて子孫を残す確率が増加するであろうが、そうでない変異をもった個体は子孫を残す確率が減少する。生物の生息環境、すなわち自然が生存闘争の勝敗の決定要因であり、生存に有利な変異は代々蓄積されて、長い歳月の後に、遂に新しい種が誕生する、というのがダーウィンのアイデアだった-「自然選択による種の起原」に他ならない。
ダーウィンは、自然選択という考えを人為選択との類比で説明する。すなわち、飼育動物や栽培植物に関して、個体に生じた変異が人間から見て有用だと判断された場合、その変異は代々蓄積されて拡大され、遂に新種の誕生へとつながる。つまり、飼育動物や栽培植物は、動物ないし植物自身のためではなく、人間の利益ないし好みによる継続的な選択によって形成されたと考えることができる(第1章「飼育栽培下での変異」)。自然状態にある生物個体にも、さまざまな変異が生じる(第2章「自然の下での変異」)。これらの変異をもった個体のうち、厳しい自然環境下での生存闘争の中で、生存や子孫を残すのに最も有利な変異をもった個体が生き延びて子孫を残す。そして、その変異は保存され、代々累積していくであろう(第3章「生存闘争」および第4章「自然選択、すなわち最適者の生存」)。しかし、当時は遺伝のメカニズムが知られていなかったことなど、この理論は難点をもっていた。ダーウィン自身このことに気付いていており、あらかじめ反論を用意している(第6章「この学説の難点」など)。ダーウィンは、ビーグル号による航海の経験を踏まえて、生物の地理的分布に着目しており(第11章および第12章「地理的分布」「同(続)」)、生態学の基本的な視点を確立した。
◆読み方
生物種は不変ではなく、変化ないし進化するという考えは、獲得形質遺伝説で有名なフランスのJ.P.ラマルクをはじめ、ダーウィン以前にも何人もの人々が提唱していた。しかし彼らは進化のメカニズムを十分な論拠をもって解明することはできなかった。しかも、生物進化の問題は、当然のことながら、人間とは何か、人間と他の生物との間には決定的な違いはあるのか、といったキリスト教信仰の根幹に関わる深刻な問題に通じている。そのため、ダーウィンは自らの考えを公表することに非常に慎重であり、長年にわたって、証拠を整えることに、また明解な論理を構築することに専念していた。
このようなダーウィンの慎重な姿勢を変えさせたのは、本書「序言」でダーウィン自身が証言しているように、1858年6月に届いたA.R.ウォレスからの手紙と論文草稿であった。その論文...