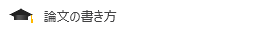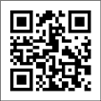資料紹介
賢治作品におけるオノマトペを、演劇論・色彩論・絵画論を引用しながら論ずる。聴覚表現と視覚表現との違い、その情と智への傾きに着目し、「風」のキーワードのもとにそのあり方を探る。
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
賢治作品における「音」〜風としてのオノマトペについて〜
「りうりう」
「フィーガロ、フィガロト、フィガロット」
「どっこどっこ」
「どう」
「どっどど どどうど どどうど どどう」
宮沢賢治の文学作品を読むとき、「風」はとても印象深く胸に残る。「風が吹きました」とだけ描かれているのでもなければ、「びゅう」とか「ぴゅう」といった、ありきたりの擬音語に筆を任せることもされていない。
「日本人は古来から風好きであろう」との見解がある。芭蕉が「秋来ぬと〜」の句で詠ったように風の音に心を動かすことは、詩人にとってその感受性の資質を問われるひとつの基準ですらあったのではないか──鈴木忠志はそう著書のなかで語っている。そのゆえんは、梅原猛の論によるところの、「風とは自然のけはいである」というものらしい。
古来の伝統につらなって、風は今日においても情緒的な反応を期待する要素として、演劇で効果音として使用される例が多い。しかし、同じように演劇で「情緒的な喚起力のある自然物としてたえず利用してきた雪や月や花」と風とが大きく異なるのは、前者が視覚的存在であり、後者が聴覚的存在である点だろう。そのため風...