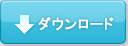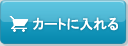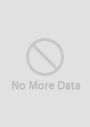資料紹介
A+判定を頂きました。ぜひ参考にしてみてください^^
(参考図書:中嶋洋一, 幸若晴子, 大津由紀雄, 柳瀬陽介, 佐藤礼恵, 『15(フィフティーン)―中学生の英詩が教えてくれること かつて15歳だった全ての大人たちへ』, ベネッセコーポレーション, 2006)
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
「言葉を教える者としてどうあるべきか」
はじめに
言葉は時に人を喜ばせ、時に怒らせ、時に悲しませ、そして時には奈落の底に落ちたような気分にもさせる。そのことから言葉には霊が宿っているとされ、「言霊」という言葉もあるほどだ。そんな中で、どの場面でどのような言葉遣いをできるかというのはかなり重要なものであり、ひいてはこの能力で人間性を判断されるといっても過言ではない。
その能力の高い低いは、親はもちろん、小・中学校で言葉を教えてもらった教師からどのような教育を受けてきたかに左右されるところが大きい。
言葉の表現豊かな子どもたちに育てるため、教師にはいったいどのような資質が求められるのか。
本レポートでは、課題図書『15(フィフティーン)―中学生の英詩が教えてくれること かつて15歳だった全ての大人たちへ』を読んで共感したキーワードをもとに自分の考えを交えながら、私が考える、言葉を教える者としてどうあるべきか、という点について述べていきたい。
教師の資質
教師のボキャブラリー
まずは生徒に言葉を教える大前提として、教師が豊富なボキャブラリーを兼ね備えていることが求められる。
た...