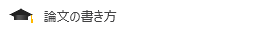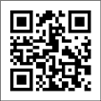資料紹介
宗教論の講義は、世界には様々な宗教があり、その数だけ様々な価値観があるということを改めて確認することで、昨今の世界情勢と密接に関わる「宗教」というものを足元から見つめ直すいい機会になった。
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
宗教と人権の制約
宗教論の講義は、世界には様々な宗教があり、その数だけ様々な価値観があるということを改めて確認することで、昨今の世界情勢と密接に関わる「宗教」というものを足元から見つめ直すいい機会になった。授業が開講される前は、様々な宗教的慣習の中には到底理解しがたいようなことがあるのかもしれないなどと色々想像を巡らしていた。それと同時に、「世界は多様、宗教も多様」という認識を大前提にそれほど驚くようなことはないだろうと高をくくっていたので、初めてクマリ信仰の存在を知ったときのインパクトは大きかった。この講義で一番印象深かったクマリ信仰について述べたい。
ネパールのカトマンズに古くから伝わるクマリ信仰は、まだ世の右も左もわからないような幼い少女を「生ける神」(クマリ)として崇拝するという宗教的慣習である。クマリは額に第3の目を持ち(額に描かれる)、多種多様な願いを抱く人々の前でも決して表情を崩すことはない。その視線の動き1つで、国の行く末を予見すると信じられており、一挙手一投足が常に注目されるほどの絶対的な影響力を持っている。神は「女」になる前の少女に宿るという考え方に基づいて、1人のクマリは「女」になるまでの期間、クマリであり続ける。クマリとなった少女はクマリ専用の館のような場所で暮らす。クマリは幼児期の一定期間を事実上の幽閉ともいえる状況下で過ごすので、学校にも行けず、一般人と気軽にしゃべることもままならない。1人のクマリが「女」になると、そのクマリは「クマリ」から普通の少女となり、後継となるクマリの選定が始まる。クマリでなくなった少女は、クマリ時代とは180度正反対の一般的な日常生活に戻ることになる。当然そのときには同年代の少女に比べると、学習面などで遅れをとっている。
このクマリ信仰の存在を知るまで、「生ける神」の存在を全く知らなかったわけではない。チベットのダライ・ラマが「神」として代々、人々から崇拝の対象になっていることはニュースや新聞記事などで目にしたことがあった。ダライ・ラマを中心としたチベットの独立問題に対する諸外国のスタンスを見ても、「生ける神」という概念自体は世界的にもそれほど特殊なことではないように思われる。このようにダライ・ラマに代表されるような「生ける神」が広く認知されていることに加え、私は現代の大多数の日本人と同様に、初詣や七五三をとりわけ宗教的慣習と意識せずに古くからの伝統的慣習と捉え、幼いころから宮崎アニメなどを通してアニミズムに親近感を抱いていたので、「生ける神」という概念自体にさほど違和感を覚えなかった。
しかしこのクマリ信仰は、私の目には特殊に映った。見るからにあどけなさの残る少女が、無表情な「神」であるということに大変驚いたと同時に、クマリの少女をみているうちに日本の天皇を想起した。一般人から選定され、少女の間だけ「神」として崇められるクマリと、代々受け継がれてきた血統を重視し、戦後に日本国憲法の下で「象徴」となった天皇ではたしかにその位置づけが違う。だが、皇室という存在が身近にある日本という国家の国民としては、天皇とクマリがどうしても重なってみえた。右も左もわからぬ頃から崇められる存在としての宿命を負わされ、神聖なものとして育てられる点では同じであろう。期限付きの「神」と、象徴としての永久的な事実上の神という点を別にすれば。つまり、クマリは生まれたときからクマリというわけではなく、その「神」としての地位は永遠ではない。それに対して戦後も皇室という大枠がしっかりと残された日本では、天皇に限らず皇室で生まれた者は生まれてから一生皇族であり続ける(昨年、民間人の黒田さんとご結婚なさった紀宮様のようなケースは別として)。この境遇の格差だけみると、クマリが非常に不憫に思える。クマリは生涯、神であり続ける必要がない分、窮屈な思いを抱き続ける必要はないが、それは突然「神」でなくなり、俗世間に溶け込まなければならない日がやってくることも意味している。皇室のように幼いころからの教育方針が確立されていない上に、クマリであるうちは教育を受けられないシステムでは、「神」でなくなったとき一番苦労を強いられてしまうのはクマリ自身である。宗教的慣習の中で、人権が制約されてしまうパターンはどんな宗教にも多かれ少なかれあるだろう。しかし、どんな宗教でも最低限度の配慮が施されているのではないだろうか。たとえばイスラムのラマダンでは、子ども、老人、病人などは体力面で弱者であるということを考慮して、ラマダンをしなくてもよいと定められているように。ラマダンは生命に直接関わってくる問題である一方で、クマリ信仰はクマリが外部との接触を断たれ、教育を受けられないものの、直接生命の危機に晒されないので比較するのには適していないかもしれない。しかし、ラマダンがイスラム教徒全体にとっての共通の宗教的慣習であるのに対して、クマリ信仰におけるクマリの選定は、クマリを信仰する人々にとっては信仰の対象である「神」が選定される慣習であるのと同時に、クマリとなる一少女にとっては人権を制約される側面を持つ。立場により、慣習の性格が異なってくるのである。幼い少女がクマリになった時点で、教育を受ける権利を制約されてしまうということと、皇族が確立された教育方針の下で育つことを比較すると、クマリから一般人になるときに備えて最低限の教育が同年代の少女のように受けられるシステムが検討されてもいいのではないかと思える。個別の宗教的慣習に対して、部外者が干渉するのは適切ではないことは重々承知している。また現実問題として、古くからの宗教的かつ歴史的な慣習を変えることは、限りなく不可能に等しいことかもしれない。しかし、ひとえに「宗教的慣習」の名のもとに、一個人の人権が制約されてしまうのはやむを得ないと言い切れるだろうか。現代でも制度化され、存続されている皇室(王室)でさえ、その当事者である皇族(王族)は極度の精神的な緊張を強いられるのだから、クマリの精神は知らず知らずのうちに相当の重圧を抱えているのではないだろうか。やはり、クマリ信仰をいわゆる王室(皇室)制度と比較すると、クマリに対するアフターフォローが充実していないように感じる。いくら自我に目覚める途上にある少女だとしても、何の前触れもなく「神」という重責を担わせるのならば、尊厳だけでなく、一少女の自由を制約することの重みを人々が認識し、それ相応の責任を持つのが筋のように思う。クマリ信仰には、宗教と人権の整合性をとることの難しさを深く考えさせられた。