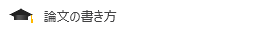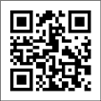資料紹介
刑法における新旧学派の争いについて述べよ。
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
新旧学派の争いとは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて犯罪と刑罰の理解を巡り、古典学派(旧派)と近代学派(新派)の間で展開された刑法理論全般にわたる論争である。
キリスト教神学の支配下にあったアンシャン・レジームの刑法は、しばしば人民を処罰の恐怖により威嚇し服従させるための手段として利用され、非合理的、擅断的、威嚇的、身分的、宗教的な思想が支配していた。このような特色を持つ中世の刑法を痛烈に批判したのが近代啓蒙主義の思想家であり、旧派の刑法思想の背景となる。中でも、ベッカリーアは「犯罪と刑罰」で、神の法ではなく人間のつくる法規範によってのみ刑罰は発動されるべきであるとする罪刑法定主義を唱えた。また、フォイエルバッハは法と道徳を峻別し法的権利の侵害こそが犯罪の本質であるとし、犯罪に対して与えられる苦痛を予め予告すれば犯罪をやめるという心理強制説を唱え罪刑法定主義を裏付けた。その後、旧派の刑法思想に大きな影響を及ぼしたカントは、人格主義と自由意思論を前提として刑罰は犯罪を犯したという理由だけで犯人に科されるべきであり、同害報復こそ刑罰の原理であると主張した(絶対主義的応報主義)。また...