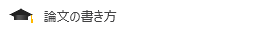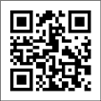資料紹介
1、はじめに
『方丈記』は、『徒然草』と並んで、日本の随筆文学の代表的古典とされている。四百字詰め原稿用紙で換算すると二十枚程度の短いものであるが、作者鴨長明は、この作品の中で、ほぼ一貫して住居に関して論じている。長明には、それに対する何か特別な思いがあったのだろうか。その点について考えてみたい。
2、父の死がもたらしたもの
「ゆく河の流れは」で始まる序文的な一節に続いて書かれているのは、安元三年の大火事件、治承四年の辻風、同年の遷都、養和の飢饉、同年の大地震である。これらの五大災厄は、長明が実体験したものだけに、緊迫感あふれるリアルな描写がされている。間に、「さしも危ふき京中の家をつくるとて、宝を費し、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る」「すべて世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなるあだなるさま、またかくのごとし」と論じているのも、体験に裏付けされた実感だろう。
災厄の部分は、それだけで作品全体の約四割を占めている。このことはつまり、「細目の描写が正確であればある程、現実に対する眼がきびしければきびしい程、それはより深き根拠を提供」(永積安明『方丈記序論』)したということになる。長明は、よりリアルに災厄を描写することで、「このように何がどうなるかわからない生きにくい世の中だから、住みかに神経をすりへらすのは愚かなことだ」という結論を、無理なく強調したのである。
では、長明自身は、どんな住みかを構えていたのだろうか。それは、自分の過去について述べた段でふれている。彼は、「三十あまりにしてさらにわが心と一つの庵をむす」んだ。それまで住んでいた家――父方の祖母の家と比べると「十分が一」だという。
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
1、はじめに
『方丈記』は、『徒然草』と並んで、日本の随筆文学の代表的古典とされている。四百字詰め原稿用紙で換算すると二十枚程度の短いものであるが、作者鴨長明は、この作品の中で、ほぼ一貫して住居に関して論じている。長明には、それに対する何か特別な思いがあったのだろうか。その点について考えてみたい。
2、父の死がもたらしたもの
「ゆく河の流れは」で始まる序文的な一節に続いて書かれているのは、安元三年の大火事件、治承四年の辻風、同年の遷都、養和の飢饉、同年の大地震である。これらの五大災厄は、長明が実体験したものだけに、緊迫感あふれるリアルな描写がされている。間に、「さしも危ふき京中の家をつくるとて、宝を費し、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る」「すべて世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなるあだなるさま、またかくのごとし」と論じているのも、体験に裏付けされた実感だろう。
災厄の部分は、それだけで作品全体の約四割を占めている。このことはつまり、「細目の描写が正確であればある程、現実に対する眼がきびしければきびしい程、それはより深き根拠を提供」(永積安明『方丈記序論』)したと...