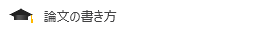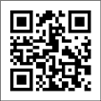資料紹介
状態の安定性
毎度、表現が大袈裟なのは気にしないように。 学習意欲を煽るのが目的なので・・・。
安定とは何か
自然は安定な状態を「好む」のだろうか。 こういう考え方をしているなら見方を変えた方がいい。 ある状態から抜け出しにくい時、その状態を安定であると考える。 つまり自然が好むかどうかは関係無く、ただなかなか抜け出せないからその状態にとどまっているだけだととらえるべきである。 安定なんていう概念はそれだけのものだ。
山の頂上にあるボールと、谷底にあるボールとどちらが安定かと言えば、谷底の方である。 前回も言ったが、自然がエネルギーの低い方を好んでいるのではない。 谷底では少し移動すると元の位置に戻す方向に力が働くので、ボールは仕方なくその辺りの位置でうろうろするしかないだけだ。 それを人間の言葉で解釈すれば、「エネルギーが低い方が安定である」となるのである。
状況により様々であって、これは基本法則などではない。 エネルギーが低い時ばかりが安定だとは限らない。
熱力学的な安定
前回は「断熱」「等温かつ定積」「等温かつ定圧」の条件下でそれぞれ、
という不等式が成り立っていることを導いた。 これらを使って、物質がどういう状態で安定して存在するかを調べる事が出来る。
例えば断熱条件で不可逆変化が起こるとエントロピー S は必ず増大する。 不可逆変化なので S が増大した状態からは自然には戻ってこない事を意味する。 もしエントロピーが極大であるような状態に一度到達すれば、そこから他の状態へは変化しようがない。 つまりそこが安定した状態なのだ。
同様に「等温かつ定積」の条件では F が極小になる状態が安定である。 この条件下ではエントロピー S は不可逆変化以外の理由でも上下するので、 S の極大で判断するわけにはいかないのだった。
同様に「等温かつ定圧」の条件では G が極小になる状態に落ち着く。
しかし系はこれらの関数 S, F, G の値の「変化」が最も急になるような道筋を選んで状態変化するわけではない。 斜面に置かれたボールの振る舞いとはちょっと違う。 もし仮に関数値の変化が急であるような道筋を選んだとしても、状態変化にかかる時間が短くなるというわけでもない。 状態図の上の距離は現実の時間とはまったく関係がないからである。
こういうわけで、ある状態から出発して、そこから到達可能な極大、極小点が複数あった場合に、系が最終的にどの状態にたどり着くか、といったことは熱力学では全く予言できないのである。 熱力学とはそういう学問であって、結果についてその状態が安定かどうかということしか言えない。 しかしそれだけでも色々な事が調べられる。
極値判定について
関数の極大、極小を求める方法については高校の数学で学んだ事だろう。 まず関数の1階微分が0になるところを見つけ、その点での2階微分の正負によって下に凸(極小)か、上に凸(極大)かを判断するのだった。 しかし熱力学に出てくる関数は変数が一つではなく複数ある。 そういう場合については恐らく高校では習ってはおるまい。
例としてある多変数の関数 g ( x, y, z ) を考えよう。 変数 ( x, y, z ) をごくわずか ( δx, δy, δz ) だけ変化させた時の関数 g の微小変化は
と表される。 いや、実はこれは、そう断言するにはあまり正確ではない。 この式は、( δx, δy, δz ) に比例するような変化のみを表していて、これらの2乗、3乗に比例する
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
状態の安定性
毎度、表現が大袈裟なのは気にしないように。 学習意欲を煽るのが目的なので・・・。
安定とは何か
自然は安定な状態を「好む」のだろうか。 こういう考え方をしているなら見方を変えた方がいい。 ある状態から抜け出しにくい時、その状態を安定であると考える。 つまり自然が好むかどうかは関係無く、ただなかなか抜け出せないからその状態にとどまっているだけだととらえるべきである。 安定なんていう概念はそれだけのものだ。
山の頂上にあるボールと、谷底にあるボールとどちらが安定かと言えば、谷底の方である。 前回も言ったが、自然がエネルギーの低い方を好んでいるのではない。 谷底では少し移動すると元の位置に戻す方向に力が働くので、ボールは仕方なくその辺りの位置でうろうろするしかないだけだ。 それを人間の言葉で解釈すれば、「エネルギーが低い方が安定である」となるのである。
状況により様々であって、これは基本法則などではない。 エネルギーが低い時ばかりが安定だとは限らない。
熱力学的な安定
前回は「断熱」「等温かつ定積」「等温かつ定圧」の条件下でそれぞれ、
という不等式が成り立っていることを導いた。 これらを使って、物質がどういう状態で安定して存在するかを調べる事が出来る。
例えば断熱条件で不可逆変化が起こるとエントロピー S は必ず増大する。 不可逆変化なので S が増大した状態からは自然には戻ってこない事を意味する。 もしエントロピーが極大であるような状態に一度到達すれば、そこから他の状態へは変化しようがない。 つまりそこが安定した状態なのだ。
同様に「等温かつ定積」の条件では F が極小になる状態が安定である。 この条件下ではエントロピー S は不可逆変化以外の理由でも上下するので、 S の極大で判断するわけにはいかないのだった。
同様に「等温かつ定圧」の条件では G が極小になる状態に落ち着く。
しかし系はこれらの関数 S, F, G の値の「変化」が最も急になるような道筋を選んで状態変化するわけではない。 斜面に置かれたボールの振る舞いとはちょっと違う。 もし仮に関数値の変化が急であるような道筋を選んだとしても、状態変化にかかる時間が短くなるというわけでもない。 状態図の上の距離は現実の時間とはまったく関係がないからである。
こういうわけで、ある状態から出発して、そこから到達可能な極大、極小点が複数あった場合に、系が最終的にどの状態にたどり着くか、といったことは熱力学では全く予言できないのである。 熱力学とはそういう学問であって、結果についてその状態が安定かどうかということしか言えない。 しかしそれだけでも色々な事が調べられる。
極値判定について
関数の極大、極小を求める方法については高校の数学で学んだ事だろう。 まず関数の1階微分が0になるところを見つけ、その点での2階微分の正負によって下に凸(極小)か、上に凸(極大)かを判断するのだった。 しかし熱力学に出てくる関数は変数が一つではなく複数ある。 そういう場合については恐らく高校では習ってはおるまい。
例としてある多変数の関数 g ( x, y, z ) を考えよう。 変数 ( x, y, z ) をごくわずか ( δx, δy, δz ) だけ変化させた時の関数 g の微小変化は
と表される。 いや、実はこれは、そう断言するにはあまり正確ではない。 この式は、( δx, δy, δz ) に比例するような変化のみを表していて、これらの2乗、3乗に比例する高次の項を含んでいないからである。 それでこの変化分は「1次の変分」と呼んでおくべきだ。 変分と言うと専門的に聞こえるが、「変化分」と呼べばいいものをかっこつけてそう呼んでいるだけなのであまり構えなくてもいい。 ちなみに、もし変数の変化が無限小なら高次の項は無視できることになり、この式でも十分正確である。 その場合には変分記号 δ の代わりに、微分記号 d を使って書いたであろう。 変分と微分の違いはそういうところだ。
高校で習う1変数の関数 f (x) のグラフが水平となる条件というのは、 x が無限小変化しても f がそれに比例するような大きな変化をしないことであった。 (極限を取るので x に比例する以外の高次の項は無視してよいのだった。) 同じように多変数関数 g が極値を取るところでは、 x, y, z のいずれを動かしても大きな変化のないことが必要である。 つまり、この式の全ての項の係数が皆0であればいいのである。 この考えが1変数の1階微分の代わりに使える。
では2階微分に相当するものはどう考えればいいだろう。 2階微分は「変化分がどう変化するか」という意味だと解釈できるのだった。 しかし変数が多数あると、それぞれの変数による変化分が、それぞれの変数に影響されるのであって、非常にややこしいことになる。 ややこしいだけでそれほど難しくはない。 実際、次のようになる。
これは変数の2次の変化に比例する量なので「2次の変分」と呼ばれる。 式の全体に (1/2) がついているのは、1変数のみの関数 f(x) のテイラー展開が、
と表されるのと同じ理屈であって、この式の第3項目がそれに相当している。 変化分が変化に比例しながら加わっていくので、幾何学的に考えれば三角形の面積を求めるのと同じ形式になっているわけだ。 この辺りの細かい理屈が気になる人は数学の教科書で調べて欲しい。
δ2g がどんな変数の変化に対しても常に正ならばそこは極小点であり、常に負になるならば極大点だということになる。 しかしその判定はなかなか難しい。 もし δx2, δy2, δz2 といった2乗の項しかなければ、全ての項の係数が全て正か全て負かという単純な話でいいのだろうが、 δxδy などのような項が含まれている場合は δx が正でも δy は負になるかも知れないし、その場合にその変化が他の項にちゃんと打ち消されるかどうかという判断が非常に面倒だ。 そのために「ヘッセ行列」というものを考える。
「この行列の固有値が全て正値ならば極小で、全て負値ならば極大である。」 ・・・と言われてもその計算は面倒であって、あまり助けにはならない。 ただ2行2列の場合、すなわち2変数関数の場合に限っては便利な定理がある。 「このヘッセ行列の行列式の値が正であり、かつ行列の左上の成分が正であるなら(この時、行列式が正なので当然右下も正であるが)、関数は極小であり、逆にこの行列の行列式が正であり、かつ行列の左上の成分が負である時には極大である」ことが言える。 細かい部分については線形代数の教科書で「2次形式」の辺りを調べてみて欲しい。
以上が多変数関数の極値判定に関する大まかな状況である。 これらのことを使って2つほど簡単な例題をやってみよう。
熱平衡
断熱シリンダーに気体が密封されており、熱を通す壁で2つの部分 A, B に仕切られているとする。 この壁は固定されているとする。
全体のエントロピー S は、A, B それぞれの部分のエントロピーの合計であって、
と表せる。 ここで S を U と V の関数として表しているのは、今後の計算に少々都合がいいからであって、他の変数を選ぶと計算が出来なくなるわけでもない。
ここで、δS を計算してやると、
となるが、今回は体積は変化しないので、
としておけばいい。 偏微分のところは、前に導いた関係を使って、
と変形できる。 これは理想気体に限らず成り立つのだった。 この結果をさらに簡単な形にまとめてやりたい。 うまい具合に、A, B の間でやり取りされる内部エネルギーは保存するので、
という拘束条件がついており、これを使えば、
のように非常に簡単な形にまとめられる。 そしてこれが Ua の変化に対して0であるためには
が成り立っていればいい事が分かるのである。
つまり A, B の温度が等しくなるところが安定な状態だと言っているわけで、自然に熱平衡に落ち着くことを表しているのだ。 しかしこれを見て「熱力学の第0法則」は不要だったなどと考えてはいけない。 ここまでの議論は第0法則を前提にして導かれてきたわけで、ここはそれに反する結果が出なくて良かったと胸を撫で下ろすべき場面である。
さて、もう一つの条件「これは本当に極大点なのか」ということを確かめておこう。 この例題では体積が変化しないので、1変数の関数と変わらない。 それで普通に2階微分を計算してやればいい。
S が極大になる条件はこの各項の係数が負になることである。 温度 T や モル数 n などは当然正値であるので特に考える必要もないが、定積比熱 Cv の正負についてはまだこれまで考えたことがなかった。 つまり、
が平衡の条件だということが言える。
さて、これを根拠にして Cv は必ず正でなければならないことがあたかも証明されたかのように書いてある教科書があるが、誤解せぬよう注意して読むようにしよう。 もし Cv が負になっている場合があれば、その時には安定しないと言っているだけだ。
もし Cv が負であると、熱が流入するほど温度が下がることになる。 逆に熱が逃げるほど温度が上がる。 そんなバカな、と思う人はこんな議論はしないで Cv が正であることを根拠もなく疑いもせずに信じていればいい。 しかしそういうことだってあるかも知れないではないか。 Cv が常に負だというのでは経験に...