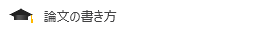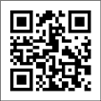資料紹介
蒸気機関の歴史
巨大な蒸気機関が動くさまはメッチャカッコいいよね。
ニューコメンの大気圧機関
気体を熱すれば強い力で膨らむ。 それを冷やせば再び強い力で収縮する。 この力を利用すれば、人間や馬が重労働をしなくても済む。 ただ熱したり冷やしたりを繰り返すだけでいいのだ。 そう考えてニューコメン氏は蒸気機関を作った。(1732,1712)
炭坑を掘ると水が染み出してくる。 掘れば掘るほど大量の水が出る。 放っておくと坑道は水没する。 それを汲み出すために大量の馬を使って昼夜を分かたずポンプを動かし続けたのだが、馬の飼育費のために採算が取れなくなってしまった。
蒸気機関をこの馬の代わりに使おうというのだ。 一分間に12ストロークだったそうだ。 つまり5秒で1往復か。 思ったより速い。 しかし歴史資料館などで実物が動いているのを見るとかなりゆっくりに感じる。 蒸気機関車の力強さと比べてしまうからだろうか。
ニューコメン氏の蒸気機関では、水を汲み出すために、掘り出された石炭の4割ほどを燃やさなくてはならなかったらしい。 それでも50年近くは実用的に使われていたようなので馬を飼うよりはまだましだったのだろう。
ニューコメン氏のやり方は単純だった。 水を沸騰させて作った蒸気をシリンダーに導くことでピストンを動かし、その後、シリンダーの中に水を直接吹き入れて蒸気を冷やすというやり方だった。 冷えた蒸気は水に戻り、シリンダーの中はほぼ真空になる。 すると大気圧の力がそれを押し潰そうとしてピストンが元に戻る。 このことからこの方式は「大気圧機関」と呼ばれている。
高圧機関の恐怖
単純な仕組みとは言え、シリンダーを直接火にかけるような効率の悪いことをしなかったのは大した工夫だと言える。 しかしこれは彼の発明ではない。 実は彼以前にセーヴァリーという人が蒸気の圧力を利用したポンプを作っている。(1702) ニューコメン氏はこのセーヴァリー氏に特許料を支払って自分の装置を売っていた。
セーヴァリー氏の装置はどんなものだったのだろうか? まだ「蒸気機関」と呼べるものではない。 容器に溜まった水を蒸気の圧力で上へ押し出し、蒸気が縮む時の力で下から水を吸い上げるという、今でも家庭で使われている灯油ポンプと同じような仕組みのものだ。 ボイラーで水を沸かして作った蒸気を必要に応じて別の容器に導き入れるというアイデアはこの時に使われていた。 容器に水をかけて冷やすのも同じだ。 この装置にはピストンはなく、弁も自動化されているわけではなかった。 しかし、熱を力に変えるという点では蒸気機関の始まりと言えるかも知れない。
ただしこの装置は高圧蒸気を利用していたために爆発事故が良く起こった。 鉄の固まりが沸騰した熱湯と高温の蒸気とともに吹っ飛ぶのだ。 まさに爆弾そのものである。 このようなものには近寄りたくない。 すでに数万人(!)もの技術者たちがこの事故の犠牲になっている。 「大気圧機関」の発明はその問題を解決するために生まれたのである。 ニューコメン機関では蒸気の注入、水掛け作業も自動化してあったわけで、基本的なアイデアはこれで出揃ったわけだ。
ワットの改良
ニューコメン氏の機関を改良したのがワット氏の蒸気機関だ。(1772) 壊れたニューコメン機関を修理して欲しいと頼まれたのがきっかけだそうだ。 それから12年かけて、彼は4倍も効率を高めるのに成功した。 400%の効率改善! これは偉大な功績だ。 せっかく掘り出した貴重な燃料を以前の 1/4 しか
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
蒸気機関の歴史
巨大な蒸気機関が動くさまはメッチャカッコいいよね。
ニューコメンの大気圧機関
気体を熱すれば強い力で膨らむ。 それを冷やせば再び強い力で収縮する。 この力を利用すれば、人間や馬が重労働をしなくても済む。 ただ熱したり冷やしたりを繰り返すだけでいいのだ。 そう考えてニューコメン氏は蒸気機関を作った。(1732,1712)
炭坑を掘ると水が染み出してくる。 掘れば掘るほど大量の水が出る。 放っておくと坑道は水没する。 それを汲み出すために大量の馬を使って昼夜を分かたずポンプを動かし続けたのだが、馬の飼育費のために採算が取れなくなってしまった。
蒸気機関をこの馬の代わりに使おうというのだ。 一分間に12ストロークだったそうだ。 つまり5秒で1往復か。 思ったより速い。 しかし歴史資料館などで実物が動いているのを見るとかなりゆっくりに感じる。 蒸気機関車の力強さと比べてしまうからだろうか。
ニューコメン氏の蒸気機関では、水を汲み出すために、掘り出された石炭の4割ほどを燃やさなくてはならなかったらしい。 それでも50年近くは実用的に使われていたようなので馬を飼うよりはまだましだったのだろう。
ニューコメン氏のやり方は単純だった。 水を沸騰させて作った蒸気をシリンダーに導くことでピストンを動かし、その後、シリンダーの中に水を直接吹き入れて蒸気を冷やすというやり方だった。 冷えた蒸気は水に戻り、シリンダーの中はほぼ真空になる。 すると大気圧の力がそれを押し潰そうとしてピストンが元に戻る。 このことからこの方式は「大気圧機関」と呼ばれている。
高圧機関の恐怖
単純な仕組みとは言え、シリンダーを直接火にかけるような効率の悪いことをしなかったのは大した工夫だと言える。 しかしこれは彼の発明ではない。 実は彼以前にセーヴァリーという人が蒸気の圧力を利用したポンプを作っている。(1702) ニューコメン氏はこのセーヴァリー氏に特許料を支払って自分の装置を売っていた。
セーヴァリー氏の装置はどんなものだったのだろうか? まだ「蒸気機関」と呼べるものではない。 容器に溜まった水を蒸気の圧力で上へ押し出し、蒸気が縮む時の力で下から水を吸い上げるという、今でも家庭で使われている灯油ポンプと同じような仕組みのものだ。 ボイラーで水を沸かして作った蒸気を必要に応じて別の容器に導き入れるというアイデアはこの時に使われていた。 容器に水をかけて冷やすのも同じだ。 この装置にはピストンはなく、弁も自動化されているわけではなかった。 しかし、熱を力に変えるという点では蒸気機関の始まりと言えるかも知れない。
ただしこの装置は高圧蒸気を利用していたために爆発事故が良く起こった。 鉄の固まりが沸騰した熱湯と高温の蒸気とともに吹っ飛ぶのだ。 まさに爆弾そのものである。 このようなものには近寄りたくない。 すでに数万人(!)もの技術者たちがこの事故の犠牲になっている。 「大気圧機関」の発明はその問題を解決するために生まれたのである。 ニューコメン機関では蒸気の注入、水掛け作業も自動化してあったわけで、基本的なアイデアはこれで出揃ったわけだ。
ワットの改良
ニューコメン氏の機関を改良したのがワット氏の蒸気機関だ。(1772) 壊れたニューコメン機関を修理して欲しいと頼まれたのがきっかけだそうだ。 それから12年かけて、彼は4倍も効率を高めるのに成功した。 400%の効率改善! これは偉大な功績だ。 せっかく掘り出した貴重な燃料を以前の 1/4 しか燃やさないで済むのだから。 彼の装置はすぐにあちこちの鉱山や工場で取り入れられ、ニューコメン氏の存在はすっかり影の薄いものになってしまった。
ワット氏はシリンダーの中で蒸気を冷やすのではなく、復水器という装置を作って外部で冷やすようにした。 シリンダー自体を温めたり冷やしたりしない分だけロスが少なくて済むわけだ。 さらに、ニューコメン機関では冷えた蒸気が縮む時の「引きの力」だけを使ってポンプを動かしていたわけだが、ピストンの往復運動を回転運動に変える機構を追加することで、蒸気を注入する時の「押しの力」も動力として利用できるようにした。 それでも「大気圧機関」であることには変わりない。 「高圧機関」は危険すぎて手が出せなかったのだ。
その後、彼はシリンダーの両側から交互に蒸気を入れることで「押し」にも「引き」にも蒸気圧を使うことの出来る「複動機関」を開発(1782)した。 これが高圧機関への道を備えることになったのだが、やはり安全のために蒸気圧は上げないままだった。 他の者にも「高圧蒸気は使うな」と厳しく禁じていたようだ。 ボイラー事故の危険を身に染みて受け止めていたのだろう。
彼は他にも色々な改良をしたが、つまりはいかに少ない燃料から効率よく多くの動力を生み出すことが出来るか、というのが最大の課題だったわけだ。
高圧機関の実用化
その後、トレビシック氏が高圧蒸気を利用するのに成功する。 これにより機関の大きさが 1/5 にまで小さく出来るようになった。 こうして機関車が実用化できる準備が整ったわけだ。 その後も開発は進み、強力な機関が次々に誕生した。 ワット氏は彼の才能に嫉妬して、彼の事業を妨害しようと必死だったようだ。
石炭は初めは製鉄のために掘り出されていたのだった。 そして蒸気機関はそれを助けるために開発された。 しかし蒸気機関は、水車や風車などと違って場所に制限なく使えるという利点もあり、あちこちの機織り工場などで利用されることになった。 それであっという間に産業構造が変わり、蒸気機関のために石炭が掘り出されるようになるという逆転が起きるまでになってしまった。
産業革命だ!
初めのセーヴァリのポンプが1馬力。 ニューコメン機関で10馬力。 ワット機関で50馬力。 高圧機関で100馬力。 18世紀になると2000馬力を超えるものも登場した。 そういった開発競争の中で熱力学は発展した。 効率の良い蒸気機関を作るために必要な条件とは一体何なのだろうか? 注いだ熱を全て動力に替えることは出来るだろうか。 それを理論的に導いてより良い商品開発に応用しようとしたのである。
スターリング機関
熱力学への導入の話としてはこれくらいで十分なのだが、これら蒸気機関が過ぎ去った時代の話だと思われたくはないのでもう少し話を続けよう。
上で話した蒸気機関とは少し変わった方式の機関が存在する。 スターリング氏が開発した(1816)「スターリング機関」だ。 「スターリングエンジン」で検索をかければ分かり易く図解されたウェブページが見付かるだろうが、ここでは文章だけでも理解できるように出来る限り努力してみよう。
この方式ではシリンダーを直接温める。 効率が悪いだろうと思ったら大間違い。 これが他の機関と比べてもかなりの高性能なのだ。 シリンダーの中には「ディスプレイサー」と呼ばれる大きめのピストンが入っていて、シリンダー内のかなりの体積を占めている。 このピストンは動力を得るためのものではなく、中の空気を移動させるためのものである。 今、シリンダーの一方を温めると、その熱で中の空気が膨張する。 膨張した空気は、このシリンダーから押し出されて、別のシリンダーに入り、そこのピストンを押す。 これで動力が得られる。 押しただけではそれで終わりである。 さて、元に戻すにはどうしたらいいだろう。 初めに出てきた、空気を移動させるためのピストン、「ディスプレイサー」を動かしてやる。 実はこのディスプレイサーはぶかぶかであって、空気は隙間を通ってシリンダーの反対側へ逃げて行く。 シリンダーの反対側は冷たいので空気は縮む。 すると、先ほど出て行った空気が戻ってきて、別のシリンダーのピストンを引き戻す。 ここでまた動力が得られる。 つまり、このぶかぶかのディスプレイサーを移動させるだけで別のピストンから動力が得られることになるのだ。 では、この動力を使ってディスプレイサーを移動させてやったらどうなるだろうか。 勝手に動き続けるのである。 ディスプレイサーには圧力が掛かっているわけではないので動かすのにほとんどエネルギーは要らないことに注意しよう。
この方式のエンジンも当時かなり作られたようだが、もっと別の方式のエンジンが作られるようになったため、やがて使われなくなってしまった。
内燃機関の時代
燃料をシリンダーの外で燃やすのではなく、中で直接燃やしてやればもっと効率がいいものが出来るのではないだろうか? 現在の車のエンジンなどと同じ方式、「内燃機関」の始まりである。 実際はこの方式は蒸気機関にヒントを得て思いついたものではなく、蒸気機関のかなり前からも色々試されてはいたようである。 ピストンの中で火薬を爆発させる「爆発機関」や、石炭の粉末を放り込んで燃やす「石炭エンジン」なども古くから作られている。 しかし燃料として揮発性の高い「ガソリン」が使われだしたことが、この方式を普及させるきっかけとなった。
内燃機関についても熱力学と無関係ではないが、ここでは詳しく語るまい。 この辺りの進歩を引っ張ったのは、もはや熱力学のような理論ではなく、もっと技術的なものだろう。 この後はずっと内燃機関の時代が現代にまで続く。
ジェットエンジンも内燃機関の一種だ。 タービンを回して空気を圧縮し、ここに燃料を入れて点火し後方へ吹き出す。 その勢いを使ってタービンを回して前方からさらに空気を取り入れるという装置だ。 ...