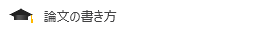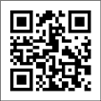資料紹介
V・H・H・グリーン『イギリスの大学--その歴史と生態』
法政大学出版局、1994年、xvii + 440 + 48頁。
訳者あとがき
本書はV.H.H. Green, The Universities(British Institutions Series), Pelican Books, 1969 の全訳である。原著名は単に『大学』であるが、邦訳タイトルは第Ⅰ部と第Ⅱ部の内容に則して『イギリス大学の歴史と生態』とした。また原著の各章は単にアステリスク(*)で区切られているだけだが、訳者の責任で各節にふさわしい見出しを付けた。
本書の著者ヴィヴィアン・H・H・グリーンは、一九一五年、イングランド中部ミドルセックスに生まれ、ケンブリッジ大学トリニティ・ホールで歴史学を専攻した。オックスフォードおよびケンブリッジ両大学から神学博士の学位を授与され、また王立歴史学会のフェローにも選ばれている。いくつかの教職を経て、一九五一年にオックスフォード大学リンカン・カレッジのフェローとなり、さらに一九七一年から八三年まで同カレッジの副学寮長、八三年から八七年まで学寮長を務めた。一九八七年には同カレッジの名誉フェローに任ぜられ現在にいたっている。このような著者の経歴が、本書に「オックスフォード・ケンブリッジ中心史観」とでも言うべき色彩を帯びさせているのであろう。
グリーンは、特に教会史と大学史に造詣が深く数多くの著書を著している。本書以外に『オックスフォード・コモン・ルーム』、『オックスフォード大学史』、『ケンブリッジ大学における宗教』、『リンカン・カレッジ共同体』、『ルネッサンスと宗教改革』、『マルティン・ルターと宗教改革』、『後期プランタジネット朝』、『ジョン・ウェズレー』『スイス・アルプス』等々がある。このように多作なグリーンではあるが、彼の著作が我が国に紹介されるのは今回が最初である。
*
イギリスの大学は、中世におけるその誕生以来今日に至るまで、イギリス社会において常に重要な社会的役割を果たし続けてきた。イギリス大学の歴史についての理解は、イギリスの歴史・社会・文化を知るためには不可欠の事柄である。しかし、我が国におけるイギリス研究の伝統と蓄積にもかかわらず、イギリス大学の歴史についての研究はほとんど等閑視されてきたと言ってよい。我が国の読者が手にしうるイギリス大学を対象にした著作といえばH・ラシュドール『大学の起源(下)』(横尾壮英訳、東洋館出版社、一九六八年)、E・アシュビー『科学革命と大学』(島田雄次郎訳、中央公論社、一九六七年〔中公文庫、一九七七年〕)およびH・パーキン『イギリスの新大学』(新掘通也監訳、東大出版会、一九七○ 年)があるくらいである。しかし前者は、もっぱら十九世紀のイギリス大学の変容をテーマにしており、後者は書名から明らかなように、一九六○年代に設立された新大学のみを扱ったものであって、ともにイギリス大学全体とその歴史を通覧することはできないという限界がある。
一方、イギリスにおける大学史研究の歴史は古く、その研究の厚みには瞠目すべきものがある。最近も『オックスフォード大学史(全七巻)』(The Histroy of the University of Oxford, O.U.P., 1983-)として長年の研究の成果が刊行され始め、すでに四巻が刊行されている(グリーンも数編の論考を寄せている)。さらに『ケンブリッジ大学史(全四巻)』(The Histroy of the University of C
タグ
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容
V・H・H・グリーン『イギリスの大学--その歴史と生態』
法政大学出版局、1994年、xvii + 440 + 48頁。
訳者あとがき
本書はV.H.H. Green, The Universities(British Institutions Series), Pelican Books, 1969 の全訳である。原著名は単に『大学』であるが、邦訳タイトルは第Ⅰ部と第Ⅱ部の内容に則して『イギリス大学の歴史と生態』とした。また原著の各章は単にアステリスク(*)で区切られているだけだが、訳者の責任で各節にふさわしい見出しを付けた。
本書の著者ヴィヴィアン・H・H・グリーンは、一九一五年、イングランド中部ミドルセックスに生まれ、ケンブリッジ大学トリニティ・ホールで歴史学を専攻した。オックスフォードおよびケンブリッジ両大学から神学博士の学位を授与され、また王立歴史学会のフェローにも選ばれている。いくつかの教職を経て、一九五一年にオックスフォード大学リンカン・カレッジのフェローとなり、さらに一九七一年から八三年まで同カレッジの副学寮長、八三年から八七年まで学寮長を務めた。一九八七年には同カレッジの名誉フェローに任ぜられ現在にいたっている。このような著者の経歴が、本書に「オックスフォード・ケンブリッジ中心史観」とでも言うべき色彩を帯びさせているのであろう。
グリーンは、特に教会史と大学史に造詣が深く数多くの著書を著している。本書以外に『オックスフォード・コモン・ルーム』、『オックスフォード大学史』、『ケンブリッジ大学における宗教』、『リンカン・カレッジ共同体』、『ルネッサンスと宗教改革』、『マルティン・ルターと宗教改革』、『後期プランタジネット朝』、『ジョン・ウェズレー』『スイス・アルプス』等々がある。このように多作なグリーンではあるが、彼の著作が我が国に紹介されるのは今回が最初である。
*
イギリスの大学は、中世におけるその誕生以来今日に至るまで、イギリス社会において常に重要な社会的役割を果たし続けてきた。イギリス大学の歴史についての理解は、イギリスの歴史・社会・文化を知るためには不可欠の事柄である。しかし、我が国におけるイギリス研究の伝統と蓄積にもかかわらず、イギリス大学の歴史についての研究はほとんど等閑視されてきたと言ってよい。我が国の読者が手にしうるイギリス大学を対象にした著作といえばH・ラシュドール『大学の起源(下)』(横尾壮英訳、東洋館出版社、一九六八年)、E・アシュビー『科学革命と大学』(島田雄次郎訳、中央公論社、一九六七年〔中公文庫、一九七七年〕)およびH・パーキン『イギリスの新大学』(新掘通也監訳、東大出版会、一九七○ 年)があるくらいである。しかし前者は、もっぱら十九世紀のイギリス大学の変容をテーマにしており、後者は書名から明らかなように、一九六○年代に設立された新大学のみを扱ったものであって、ともにイギリス大学全体とその歴史を通覧することはできないという限界がある。
一方、イギリスにおける大学史研究の歴史は古く、その研究の厚みには瞠目すべきものがある。最近も『オックスフォード大学史(全七巻)』(The Histroy of the University of Oxford, O.U.P., 1983-)として長年の研究の成果が刊行され始め、すでに四巻が刊行されている(グリーンも数編の論考を寄せている)。さらに『ケンブリッジ大学史(全四巻)』(The Histroy of the University of Cambridge, C.U.P., 1988-)や『ヨーロッパ大学史(全四巻)』(The History of European Universities, C.U.P., 1988-)もいよいよ刊行開始となった。個別大学史ならびに特定のテーマや時代に焦点を絞った研究は枚挙に暇がない。しかし、イギリスにおいてもJ・マウントフォードの『イギリス大学』J.Mountford, The British Universities, O.U.P., 1972)などの概説書がその一部に歴史的な記述を含んでいるとはいえ、中世から現代までをカバーし、スコットランドやアイルランドの大学も含めてイギリス大学の歴史を総合的な観点から論じた、簡にして要を得た通史はなかなか見当たらないのが現状である。
このような状況の中で、一九六九年に刊行されたグリーンの書物は、中世から現代に至る「イギリス大学通史」としての役割を依然として失ってはいない。また、本書は社会史的で生彩に富んだ叙述がなされており、大学と大学人をめぐる興味深いエピソードも数多く取上げられている。さらに、本書は大学以外の高等教育機関や学会・アカデミーなどの研究機関をも視野に入れて叙述を展開している。このような特色を備えた本書は、イギリスの大学や教育についての知識を求める人々にとってのみならず、広くイギリスの歴史や文学に関心をもつ人々に多くのことを示唆してくれるはずである。
*
さて、我が国ではここ数年来、大学のありかたをめぐってさまざまな論議がなされており、その帰趨は、戦後の学制改革以来の大学制度の大幅な改革=再編に至ると思われる。そして、この度の大学改革論議に際しては、歴史や設置形態を全く異にするイギリス大学の過去と現在の経験--伝統と革新への挑戦--から多くのことを学ぶことできるのではあるまいか。というのも、よく知られているように、戦前の我が国の大学はもっぱらドイツ大学をモデルとし、戦後はアメリカ流の高等教育システムを採用したわけだが、イギリス大学モデルとでも言うべき独自の教育理念や教育システムは、我が国の大学がこれまでほとんど知らないものであったからである。
例えば、ドイツ大学の研究中心主義に対して、イギリス大学は手造りの人間教育の伝統--いわゆる「ジェントルマン教育」の理念--を頑固に守っている。それは、イギリス大学が中世大学以来の「学徒の共同体」としての理念と性格を今に至るも失っていないからである。また、アメリカ型の大衆的な高等教育に対してイギリス大学は教師と学生および学生相互の人間的接触を重視する「少人数エリート型」の高等教育システムといえよう。その一方で、イギリス大学は歴史の転換点には世界に先駆けて、オープン・ユニヴァーシティに代表されるような革新的な試みにも果敢に挑戦している。このようなイギリス大学の特色は、現在、我が国で論議されているいくつかの論点、例えば大学における研究と教育との関係、教養教育と専門教育のあるべきバランス、大学の大衆化・開放と研究・教育水準の維持向上の方策などについて示唆するところが大きいといえよう。巷間に大学改革論議が溢れている中で、あえて本書を世に送ることによって、この論議に一石を投じたいと訳者らは願っている。
もっとも、我が国の大学同様、イギリス大学自体も、本書の叙述が終わっている一九六○年代末以降、未曾有の激動にさらされているが、そのあたりの事情については著者による「日本語版への序文」および訳者による「解説」を参照されたい。
*
本書の訳業に着手したのは十数年前のことであった。イギリス大学史を専攻する訳者の一人(安原)が本書の価値を知って、当時の同僚や研究仲間を誘って邦訳作業を開始し訳稿もある程度集まった。その間、安原はイギリスでの在外研究に際して原著者グリーンと面談の機会を得、邦訳の許可も得た。しかし、安原の職場が変わったことなどから作業は中断を余儀無くされた。筐底に眠っていた訳稿を取り出し、訳業を再開するまでに十余年の歳月が流れてしまった。かつて協力していただいた方々もそれぞれの任地に赴かれ、もはや面倒な邦訳作業を共にできる状況にはなかった。そのため、この度は安原と成定二人の共同作業となったが、別個の学部でそれぞれ西洋教育史と科学史を担当している二人の訳者が、それぞれの専門知識を踏まえて本書の訳業にあたったことは、総合大学における学際的な研究協力の実践といえるのではないかと密かに自負している。
コンピュータおよびワープロの発明は大学や学問の歴史にとって、紙や印刷術の発明にも匹敵する大事件だと思われるが、訳者らも訳業の中断期間中に発明され急速に普及したワープロを最大限に活用することによって本書を仕上げることができた。すなわち、かつて作成した訳稿をワープロに入力し、訳者二人でワープロの画面を見ながら、すべての章句について原文と対照しつつ入念に検討を加えるという作業を繰り返したのである。この集中的な作業は約一年半におよんだ。このような経緯から、本書に関しては全編について文字通り訳者二人の共訳となった。この過程で十数年前の訳稿は原形を止めないまでに改変されたこともあって本書は安原と成定二人の責任で刊行することとなった。かつて安原の求めに応じていくつかの章を訳出していただいた香川正弘(現在、上智大学文学部)(序文、第七章)、加藤詔士(現在、名古屋大学教育学部)(第五章、第十三章)の両氏にはこの場を借りて感謝とお詫びを申し上げたい。
*
つたない訳業とはいえ、本書が成るにあたっては多く方々の学恩を被っている。とりわけ訳者二人をそれぞれに大学史研究にいざなって下さった横尾壮英、中山茂両先生はそれぞれのお仕事を通じて、あるいは直接に、本書の訳業を励まして下さった。最後に、商業的にはとうてい成功の見込みのない本書の出版に力をかして下さり、「叢書ウニベルシタス」という本書に最もふさわしい器を用意...