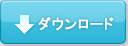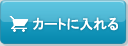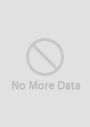資料紹介
【合格済】公衆衛生学Ⅰ 設題2 姫路大学
〈食中毒について、原因と症状、拡大防止のための手順などについて説明しなさい。〉
1696字 参考文献あり
作成の手引き
病原微生物によるもの、その他の物質によるものを解説する。
 All rights reserved.
All rights reserved.
【ご注意】該当資料の情報及び掲載内容の不法利用、無断転載・配布は著作権法違反となります。
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
設題2 食中毒について、原因と症状、拡大防止のための手順などについて説明しなさい。
初めに、食中毒とは、一般に食品を摂取することにより起こる急性胃腸炎症状を主な症状とする健康障害とされている。食品衛生法で、病因物質として「自然毒」「殺菌、ウイルス」「化学物質」「カビ」などがある。日本における食中毒自件数について、古くは自然毒によるものが半数近くを占めていたが、1970年以降現在に至るまで、微生物性食中毒が70%以上を占めている。
ここで、それぞれの病因物質について述べる。
まず、「自然毒」による食中毒は、動物性と植物性に分けられる。動物性は魚介類である。例えば、フグの内蔵には神経を麻痺させるテトロドトキシンが含まれていたり、魚類によって毒素を蓄えるものがある。植物性は、植物固有の有毒成分が毒素である。毒キノコ、有毒野素、ジャガイモの芽などによる食中毒がある。自然毒による食中毒予防には、食材の選別、除毒、解毒が必要である。
「化学物質」は、残留農薬や有害物質混入、食品変性などによる食中毒がある。残留農薬による食中毒とは、収穫した農作物をよく洗浄せずに摂取することによる急性中毒で...