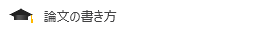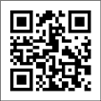資料紹介
仇討ちとその精神
「仇討ち」とは、主君や父などを殺した者を討ち取って報復することである。しかし日本人にとっては、額面以上の意味合いがあるように思われる。例を挙げるならば、1703年の元禄赤穂事件は、当時の江戸市民を異常なまでの熱狂の渦に包み込んだ。歌舞伎、人形浄瑠璃、浮世絵として四十七士の「美談」はもてはやされ、現在でもそのレパートリーを小説、映画、テレビドラマなどに広げ、人々に愛され続けている。なぜ仇討ちはこれほど深く日本人の心を掴んだのだろうか。そして、仇討ちの持つ意味とは一体何なのだろうか。
そもそも、日本における仇討ちの起源は、5世紀にまでさかのぼることが出来る。眉輪王の変(注1)は、当時の「天皇の弑逆=政権簒奪のためのクーデター」という固定観念を覆した。眉輪王を匿った円大臣をはじめ、政権からやや遠くにいた人々はこの仇討ちに同情的であり、大和時代の人々は、すでに仇討ちというものを何物にもかえがたい最重至高の人の道と考えていたようである。やがて、明治6年の太政官布告(通称:敵討禁止令)によって仇討ちは政府の公権を侵すものとして禁止されるが、仇討ちは何件か起きた。そのほとんどが処罰の対象になったが、最終的には比較的軽い刑で済まされている。敵討禁止令発布後に仇討ちし、服役していた臼井六郎(注2)の釈放祝賀会には自由民権運動の大井健太郎も出席し、「仇討ちは法的には禁止されているが、武士道の真髄であり悲願を達成し、釈放されたことはめでたい」と祝辞を述べているなど、この時代もたとえ法に反した行為だとしても、仇討ちは賛美の対象となっていたのだ。
仇討ちは、単純に肉親の情からと、主君の恩義からの2つに区分することが出来る。前者の場合、その倫理は自然発生的で、「不倶戴天の讐」という考えにおいて説明されている。つまり、「父の仇とは天を同じくすることができない。どこにいても必ず討たねばならぬ。兄弟が討たれるようなことがあれば、その場で即刻、仇を討つ。刀を取りに家に帰ったりしている余裕がない。友達の仇とは、同じ国にあることは出来ぬ。国中探し出しても仇を討たねばならぬ」ということである。しかし主君の恩義というものは、規範として儒教的倫理学を経てその上に成り立たせていると言ってよいだろう。歴史にその例を見ると、確かに主君の仇討ちは12世紀の大河兼任の乱まで待たなければならなかった。それに「不倶戴天の讐」にも君の仇についての言及はない。これは中国道徳哲学の基本の考え方に関わっているからである。中国では、人倫の大本を三綱(君臣・父子・夫婦の道)、あるいは五常(父子の親・君臣の義・夫婦の別・長幼の序・朋友の信)としているが、これらの基本道徳の中で、さらに父子の道、すなわち親に仕える孝の道をもってその本源の道としている。そして孝道が発展し、大孝として「君臣の義」が生まれたと考えられている。そこで、五経の一つ『礼記』には「孝以て君に事(つこ)う」といい、「君子の親に事うるや孝、故に忠、君に移すべし」といって、君に仕える孝がすなわち忠なのだとしている。「忠孝一本」というときも、孝が本で、忠は孝と同じだから、三段論法的に両者は一つであると認識されるのである。この関係は仇討ちの場合にも応用され、『周礼』の「君の讐は父になぞらう」と「不倶戴天の讐」とを組み合わせると、「君父の讐は共に天を戴かず」、すなわち主君の仇も必ず討たなくてはならないのである。そして、最終的には臣道としての忠義は君の仇を報ずるを究極とし、同様にして孝道は、父の仇を討つを以って最終とするという考え方になってくる。復
 All rights reserved.
All rights reserved.
資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )
仇討ちとその精神
「仇討ち」とは、主君や父などを殺した者を討ち取って報復することである。しかし日本人にとっては、額面以上の意味合いがあるように思われる。例を挙げるならば、1703年の元禄赤穂事件は、当時の江戸市民を異常なまでの熱狂の渦に包み込んだ。歌舞伎、人形浄瑠璃、浮世絵として四十七士の「美談」はもてはやされ、現在でもそのレパートリーを小説、映画、テレビドラマなどに広げ、人々に愛され続けている。なぜ仇討ちはこれほど深く日本人の心を掴んだのだろうか。そして、仇討ちの持つ意味とは一体何なのだろうか。
そもそも、日本における仇討ちの起源は、5世紀にまでさかのぼることが出来る。眉輪王の変(注1)は、当時の「天皇の弑逆=政権簒奪のためのクーデター」という固定観念を覆した。眉輪王を匿った円大臣をはじめ、政権からやや遠くにいた人々はこの仇討ちに同情的であり、大和時代の人々は、すでに仇討ちというものを何物にもかえがたい最重至高の人の道と考えていたようである。やがて、明治6年の太政官布告(通称:敵討禁止令)によって仇討ちは政府の公権を侵すものとして禁止されるが、仇討ちは何件か起きた。そのほとんどが処罰...